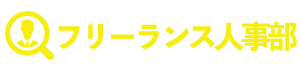業務委託契約を締結しているフリーランスを自社の従業員のように扱えば、そのフリーランスは実態としては労働者であり、業務委託契約ではなく雇用契約とみなされる場合があります。
この記事では、そもそもフリーランスとの業務委託契約とはどのような契約であるのか、また、フリーランスの労働者性の判断基準や労働者性ありとみなされるとどうなるのかなどについて説明します。
もくじ
フリーランスとの業務委託契約とは?
企業としてフリーランスと業務委託契約を締結することも増えていますが、まずは業務委託契約とはどのような契約であるのか、また、雇用契約との違いなどについて説明します。
一定の業務を委託する契約
フリーランスと締結する業務委託契約とは、その名のとおり一定の業務を委託する契約であり、一般的には次のいずれかの契約になります。
請負契約
ホームページや広告の作成、また、システム開発など、何かしらの目的物を作成、納品して欲しいときに締結する契約です。
委任・準委任契約
各種コンサルティングや社内システムの保守など法律行為以外の業務を行って欲しいときに締結する契約(準委任契約)や、弁護士に訴訟代理などの法律行為を依頼したいときに締結する契約(委任契約)です。
注意すべき点としては、上記のどちらの契約であるにせよ業務の進め方などについてあれこれと指示をしたり、業務時間を管理したりすることはできない(指揮命令権がない)ということです。
雇用契約との違い
雇用契約(労働契約)とは、業務委託契約のように一定の業務を委託するのではなく、自社の従業員として働いて欲しいときに締結する契約です。
雇用契約を締結すれば、その者を自社の従業員として指揮監督下に置くことができますが、企業側(使用者)は労働基準法やその他の法律における使用者としての責任(法定労働時間の遵守、安全・衛生の確保、災害の補償など)を負うことになります。
労働者性があれば雇用契約とみなされる場合も
フリーランスと業務委託契約を締結していたとしても、そのフリーランスに対して業務上の指示を出すなど、自社の従業員のように扱っていると、実態として雇用契約とみなされる可能性があります。
最近では、人件費の削減などを目的として、フリーランスと業務委託契約を締結しながら、従業員のように扱っている企業も見受けられます。そのような扱いを受けているフリーランスは、実態としては雇用契約であるにもかかわらず、残業代も支払われず、社会保険にも加入できないため、労働局に相談したり、裁判を起こしたりすることがあります。
このときに問題となるのが、そのフリーランスが実際に企業側の指揮監督下に置かれていたのかどうかなど、労働者性があったのかどうかという点になります。
労働者性の判断基準
請負契約や委任・準委任契約、雇用契約といった契約の形式にかかわらず、業務に従事する者に労働者性があるのかどうかの判断基準については、少し古いものになりますが、旧労働省(現厚生労働省)に設置されていた労働基準法研究会の昭和60年12月19日の報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)を参考にすることができます。
この報告では、労働基準法上の労働者に該当するのかどうかの判断基準が細かにまとめられていますが、主なポイントは次のとおりです。
※参考:大阪労働局「労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)」
1.指揮監督下で働いているかどうか
該当者が下記の状況であれば、企業の指揮監督下で働いていると言え、労働者性があるとみなされる可能性が高くなります。
- 企業からの仕事の依頼や業務上の指示を承諾するか断るかの自由がない。
- 企業から業務の内容やその遂行方法について具体的な指揮命令を受けている。
- 企業から勤務場所や勤務時間が指定されている。
- 本人に代わって他の者が労務を提供することが認められていない。
2.労務に対して報酬が支払われているかどうか
該当者の報酬が下記のように整理されていれば、労務に対して報酬が支払われている(つまり、事実上「賃金」であるということ)と言え、労働者性があるとみなされる可能性が高くなります。
- 報酬は時間給を基礎として計算されている。
- 欠勤した場合には報酬が減額される。
- 残業した場合には通常の報酬とは別の手当が支給される。
3.事業者性があるかどうか
該当者が下記の状況であれば、事業者性があると言え、逆に労働者性を弱める要素となります。
- 作業に必要な高価な機械や器具を個人で所有している。
- 報酬の額が企業で同様の業務に従事している正規従業員よりも高い。
- 業務遂行上の損害に対する責任を負っている。
- 独自の商号使用が認められている。
4.専属性があるかどうか
該当者が下記の状況であれば、企業に対して専属性があると言え、労働者性を補強する要素になります。
- 他社の業務に従事することが制度上制約され、また、時間的余裕がなく事実上困難である。
- 報酬に固定給部分があり、その額も生計を維持しうる程度のものであるなど、報酬に生活保障的な要素がある。
5.その他
その他、裁判例では、企業が該当者に対して下記のような対応をとっているのであれば、該当者の労働者性を肯定していると判断される傾向にあります。
- 採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとんど同様である。
- 報酬について給与所得としての源泉徴収を行っている。
- 労働保険の適用対象としている。
- 服務規律を適用している。
- 退職金制度、福利厚生を適用している。
労働者性ありとみなされるとどうなるのか?
上記の判断基準などにより「労働者性あり」とみなされれば、企業としては次のような対応を求められる可能性があります。
- 該当のフリーランスが希望すれば、あらためて雇用契約を締結して従業員と同様に扱わなければならない。
- これまでに未払いの残業代などがあれば、最大過去2年分(※)を支払わなければならない。
- 雇用せずに契約を解除する場合には、労働基準法上の解雇予告手当を支払わなければならない。
※2020年4月1日施行の改正民法と改正労働基準法により、2020年4月1日以降に支払われるべき賃金を請求する権利の消滅時効期間が5年(当分の間は3年で運用)になっているため、2022年4月1日以降は過去2年分以上の支払いが必要になります。
まとめ
フリーランスとの業務委託契約は、あくまで一定の業務だけをそのフリーランスに行ってもらうための契約であり、自社の従業員とする雇用契約とは根本的に異なります。
しかしながら業務委託契約を締結したフリーランスを自社の従業員のように扱えば、労働者性があるとみなされて、結果、雇用契約と同様の対応を求められることになりますので注意しましょう。
人事・労務系ライター 本田 勝志(ほんだ かつし)
中央省庁や企業(労務担当)、社会保険労務士事務所での勤務を経て、現在は人事・労務系ライターとして各種HR系サイトの記事執筆に携わる。 社会保険労務士有資格者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士